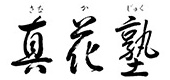裏千家茶道カテゴリー記事の一覧です
2023年10月23日
茶の湯の炭のこと

兵庫県川西市の特産で知られる「一庫炭(ひとくらずみ)」は、クヌギやカシの木を焼いて作られます。その炭の断面がまるで菊の花びらのように見えることから「菊炭」とも呼ばれます。
茶道に使う炭は、大きさや長さが厳密に決まっています。胴炭、丸ぎっちょ、割ぎっちょ、管炭、割管、添炭、枝炭とで、合わせて7種類。
炭の長さは全て同じに切り揃えられ、炉のときは二寸五分(7.5㎝)、風炉のときは二寸(6㎝)です。こうして炭から茶釜の底までの距離を同じにします。炉に使われる炭の方が長いのは、その季節が11月から4月と寒いためです。言われてみればごく当たり前のことではありますが、だからこそ「(夏は涼しく)冬暖かに」の利休七則への思いを新たにしますね。
茶の湯の炭の特長は
・しまりがあり崩れない
・樹皮が薄く密着している
・切り口に菊の花のように均一で細かい割れ目がある
・断面がまん丸に近い
などがあるそうです。
それだけでなくもちろん、炭を生産する方のネラシの加減や炭焼きの技術が重要になります。
茶の湯を学び愉しむ中で、つい自身の点前や所作の出来不出来びばかりに気を取られがちになることも多いですが、茶の湯のまさに土台を支えている炭とその生産にも心を向けて精進していきたいものです。
2019年3月2日
ひな祭り。古典から”女の子の幸せ”に思いを馳せる

明日は3月3日、ひな祭りです。写真の菓子はその名も「蛤」。貝あわせ(貝覆い、ともいまは呼ばれます)に使われる蛤の、そのどっしり座ったようなたたずまいが素敵です。(このあと、濃茶とともに皆さんでいただきました)
もともとは貝殻のもつ本来の美しさを競う遊びだったようですが、だんだんとその貝の内側に絵や和歌が描かれるようになり、いわば”蛤の神経衰弱”ともいえる、一対の貝を探し当てる遊びとなりました。蛤は、その対になっている貝同士でしかぴったりと合わないことで、仲の良い夫婦をあらわすとされています。
私(真花塾塾長)がこの貝あわせを初めて知ったのは、『徒然草』百七十一段、「貝をおほふ人の、我が前なるをばおきて、よそを見渡して、人の袖のかげ、膝の下まで目をくばる間に、前なるをば人におほはれぬ。よくおほふ人は、餘所までわりなく取るとはみえずして、近きばかりおほふやうなれど、おほくおほふなり」です。
「自分の目の前にある貝には注意が向かず、ほかの会を見渡して、人の袖の影や、膝の下にまでキョロキョロやっているうち、自分の目の前の貝を人に取られてしまう。上手でたくさん貝を取る人は、そんなに人の貝の近くまで取ると思わせないようにして、自分の近くの貝ばかりを取っているように見えるけれども、ふたを開けてみるとたくさん取ってしまう。」
あぁー修学旅行でトランプの神経衰弱したとき、こんなことあった、あった!(笑)こんな鋭い観察眼を持つ吉田兼好ってすごい。
ほかにも、兼好には賀茂際の斎宮行列を見物して騒ぐ人々の姿を冷ややかに見るエピソードがありますが、このような貝合せのような「ゲーム」にも人柄というのはよくにじみ出ますよね。
さて、いまはこのような貝合せはもちろん、お雛様の七段飾りもなかなか見なくなりましたが、やはり女の子の健やかな成長と幸せを願うというのは変わりません。幸せのかたちも、蛤のように相性ぴったりの人に添い遂げる、ということばかりではなくなってきていますが、その分ひな祭りへの思い入れも人それぞれ、ご家庭それぞれだと思います。
お菓子をいただきながら、そして一服のお茶をいただきながら、自分の人生や将来、本当の望みについて、話し合うひとときになれば幸いです。
【今回の菓子】
銘:蛤
御製:とらや